
点呼業務は、運送業界において安全運行の確保や法令順守の観点から重要な役割を担っています。2023年4月、国土交通省により点呼業務の新しい要領が施行されました。
その一つの業務後自動点呼を実施するには「機器・システム機能の要件」「機器を設置する施設・環境の要件」「運用上の遵守事項」の要領を満たす必要があります。
また、2023年5月から業務後自動点呼が開始されましたが、今後さらに実証実験や検討が進めば、業務前自動点呼の実現もそう遠くないかもしれません。現在、一部の先行実施事業において業務前自動点呼の導入が試みられており、その結果を踏まえた本格的な運用が期待されています。業務前自動点呼が導入されれば、出勤時の運転者の健康状態や飲酒の有無をより正確に確認でき、安全管理のさらなる強化が見込まれます。
この記事では、業務後自動点呼の概要や認定機器、運用の要件、自動点呼導入におけるメリット・デメリットを解説します。
目次
自動点呼とは?

自動点呼とはアルコールや病気、疲労などの確認のため、運転者の業務前後に原則対面で行う必要があった点呼業務を、ロボットなどの点呼支援機器に一部、またはすべてを代替させて行うことです。
2022年12月より業務後の自動点呼が国土交通省によって許可され、翌年1月より開始されました。運転者や運行管理者の長時間労働是正や業界全体の人手不足解消、感染症予防、点呼の確実性向上などが期待されています。
ちなみに遠隔点呼は2022年4月から、自動点呼は業務後について2022年12月から実施が認められるようになりました。
▶遠隔点呼については以下の記事で詳しく解説しています。
遠隔点呼とは?実施要領やIT点呼との違いをわかりやすく解説
業務後自動点呼実施要領の概要
国土交通省が策定した業務後自動点呼実施要領には、主に「機器・システム機能の要件」「機器を設置する施設・環境の要件」「運用上の遵守事項」が存在します。
詳細については以下のとおりです。
業務後自動点呼の要件「機器・システム機能の要件」
| ①業務後自動点呼に関する基本要件 | |
|---|---|
| 1 | 運行管理者または補助者(以下、運行管理者等という)や運転者の氏名や実施結果など業務後自動点呼に必要な確認や判断が1年間保存できる |
| 2 | なりすまし防止のため、生体認証機能がある |
| 3 | 酒気帯びの測定結果と、運転者が測定をしている様子の動画または静止画を記録・保存できる |
| 4 | 自動車や道路の状況などについて、運転者が口頭で報告した内容を記録できる |
| 5 | 運行管理者等が伝えるべきことを、運転者ごとに伝達できる |
| 6 | 運転者毎の点呼の実施予定・実施結果を、運行管理者等が確認できる |
| 7 | 運転者の呼気中にアルコールが検知された場合、運行管理者等に対し通知を発し、点呼を完了することができない機能がある |
| 8 | 業務後自動点呼に必要な確認や判断が記録されない場合や、機器に故障が発生している場合点呼を完了することができない機能がある |
| ②なりすましの防止 | |
|---|---|
| 1 | なりすましを防止するため、個人を確実に識別できる生体認証機能(顔認証や静脈認証、虹彩認証など)を備えており、識別が行われた場合のみアルコール検知器が作動する機能が必要 |
| ③運行管理者の対応が必要となる際の警報・通知 | |
|---|---|
| 1 | 業務後自動点呼は、機器がすべての判断を行うのではなく、酒気帯びの検知や機器の故障などの非常時には、運行管理者等が対応することとされている。そのため、機器には非常時に運行管理者に警報・通知を発する機能が備えられていなくてはならない。また、この機能が起動した場合点呼を完了することができない機能がある必要がある。 |
点呼結果や故障の記録は、国土交通省によって1年間保持できることが定められています。必要な内容は以下のとおりです。
| ④点呼結果・機器故障時の記録 | |
|---|---|
| 1 | 運行管理者等の氏名及び運転者の氏名 |
| 2 | 自動車登録番号 |
| 3 | 点呼日時 |
| 4 | 点呼方法 |
| 5 | アルコール測定結果及び酒気帯びの確認結果 |
| 6 | アルコール測定中及び生体認証時の静止画又は動画 |
| 7 | 点呼を受けている様子が確認できる静止画又は動画 |
| 8 | 運転者が報告した自動車、道路及び運行の状況(口頭) |
| 9 | 運転者が報告した交替運転者に対する通告(口頭) |
| 10 | その他必要な事項(口頭) |
業務後自動点呼の要件「機器を設置する施設・環境の要件」
| ①施設・環境の要件 | |
|---|---|
| 1 | 業務後自動点呼を実施する施設や環境は、なりすましやアルコール検知器の不正使用 所定の場所以外での機器の使用等を防止するため、監視カメラを備えることが必要。 |
業務後自動点呼の要件「運用上の遵守事項」
| ①事業者運行管理者等に係る遵守事項 | |
|---|---|
| 1 | 業務後自動点呼の運用に必要な事項を管理規定に明記し、運転者等、運行管理者等およびその他関係者に周知すること |
| 2 | 自動点呼機器の使用方法や故障時の対応等について運転者等、運行管理者等およびその他の関係者に適切に教育・指導をすること |
| 3 | 業務後自動点呼が指定の場所のみで実施されるよう、機器の持ち出しを防ぐ措置を講じること |
| 4 | 自動点呼機器を常に正常に動作するよう適切に使用・管理・保守すること |
| 5 | 運転者等ごとの業務後自動点呼の実施予定および結果を適宜確認し、点呼の未実施を防ぐこと |
| 6 | 自動点呼が予定時刻を過ぎても完了しない場合の適切な措置を取る体制を整えること |
| 7 | 運転者等の携行品返却の確認体制を整備すること |
| ②非常時の対応 | |
|---|---|
| 1 | 酒気帯びが検知された場合に、運行管理者等が適切な措置を講じられる体制を整備する |
| 2 | 運行管理者等に対する緊急を要する報告を、運転者ができる体制を整備する |
| 3 | 機器の故障などで自動点呼ができなくなった場合に、対面点呼等従来の方法で点呼を実施できる体制を整備する |
| ③個人情報管理に係る事項 | |
|---|---|
| 1 | 運転者等の識別に必要な生体認証符号等の取扱いについてあらかじめ対象者の同意を得ること |
自動点呼のメリット・デメリット
1. メリット
1-1. 運行管理者の負担を軽減できる
業務後点呼を機器が代行してくれるため、事務所でドライバーを待機する必要がなくなります。また運行管理者等はこれまで業務後点呼にあてていた時間を別の業務にあてられるようになります。
1-2. 人件費を削減できる
運行管理者等の負担が軽減されることから、残業時間の削減や労働環境の改善が図れることや、それに伴い残業代や深夜早朝手当など人件費が削減できます。
1-3. 点呼の確実性が向上する
点呼を機器に任せれば、確認すべき項目の漏れなどの人為的ミスがなくなります。そのため点呼の確実性の向上も期待できるでしょう。
2. デメリット
2-1. 導入に伴う運用負担
デメリットとしてまず挙げられるのは、運用のための負担が大きいことでしょう。機器の導入や運行ルール策定、運行管理者や運転者への教育体制整備などの労力がかかります。
2-2. 機器の維持・管理の負担
自動点呼のために新たな機器を導入すれば、機器が常に正常に作動するよう維持・管理しなくてはならないため、新たな労力が発生することになります。導入時のみならず、導入後もある程度の負担を要する点は意識しておきましょう。
また今回の業務後自動点呼は完全な自動化ができません。酒気帯びの検知などが発生した非常時には、運行管理者等が対応する必要があります。
業務前自動点呼について
2025年3月時点では、業務前自動点呼導入に向け実証実験が開始しています。機器だけではドライバーの健康状態確認や具体的な指示、乗務可否の判断が厳しいため、慎重な検討が必要とされています。
しかし実際に導入された場合は、従来以上に運行管理者の業務効率を向上できることでしょう。
NEWS RELEASE「クラウド型点呼システム「Cagou IT 点呼」が「業務前自動点呼」に対応 点呼の完全自動化により省人化を加速させ、運送業界の働き方改革に貢献」
まとめ
2023年4月に国土交通省によって新しい要領が施行されたことより、原則対面で行うものとされていた点呼を、認定機器によって代替可能となりました。
業務後自動点呼を実施するには「機器・システム機能の要件」「機器を設置する施設・環境の要件」「運用上の遵守事項」の要領を満たす必要があります。
自動点呼の導入によって、運行管理者等の労働時間削減やヒューマンエラー防止、安全性の向上など、ますます現場における課題解決が期待できるでしょう。
当社ではクラウド型点呼システム「Cagou IT点呼」を提供しております。ご気軽にお問い合わせください。
製品情報
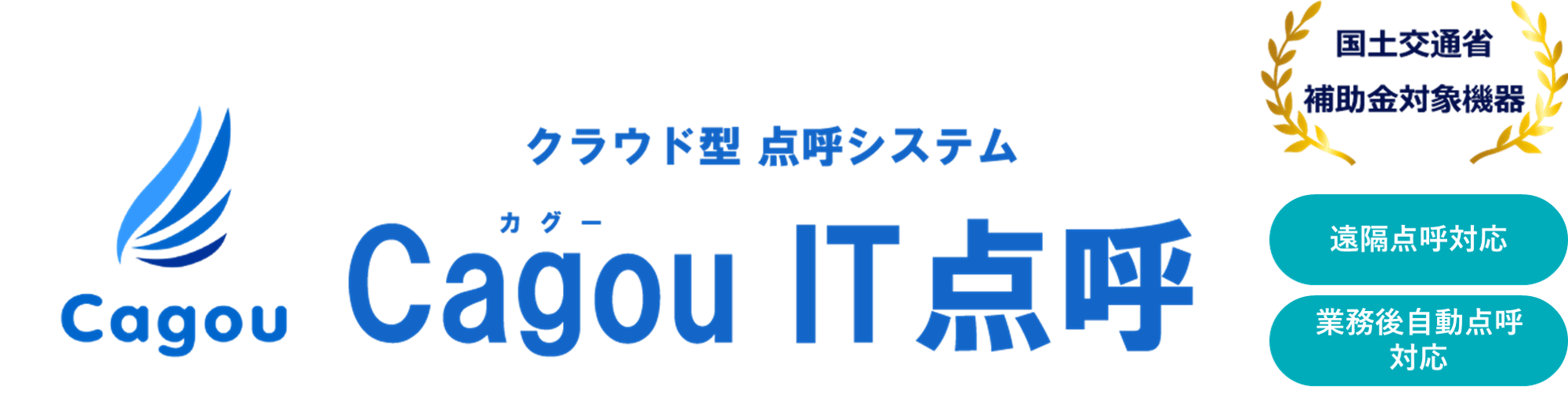 国土交通省
国土交通省補助金対象機器
旅客運送業の運輸安全を支援するクラウド型点呼支援システム。
年齢を問わないシンプルな操作性で、各種点呼手段(対面点呼・IT点呼・遠隔点呼・電話点呼)を組み合わせることにより、深夜早朝などの運用が難しい時間帯での安全確認業務を確実に実施。
利用開始時の顔認証、アルコール検知機器認証、アルコールチェック時の被点呼者の自動撮影によりなりすましを防止します。

関連リンク
- Cagou IT点呼
- クラウド型点呼システム「Cagou IT 点呼」が「業務前自動点呼」に対応 点呼の完全自動化により省人化を加速させ、運送業界の働き方改革に貢献
- 国土交通省『乗務後自動点呼実施要領』
※本記事の記載内容は2025年3月現在のものとなります。
※本事例で記載されている会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。


