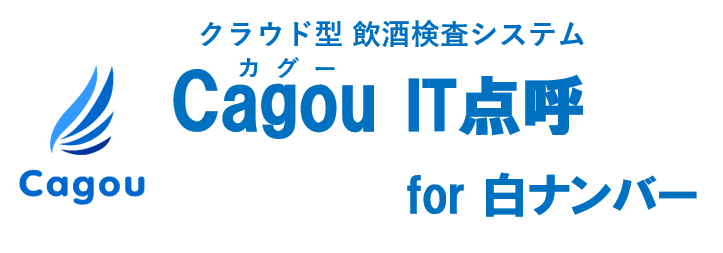2021年6月28日に千葉県八街市で起きた飲酒運転事故を受け、2022年4月に道路交通法施行規則が改正されました。白ナンバーを利用する事業者(以下、白ナンバー事業者)に対しても、2023年12月1日よりアルコールチェックが義務づけられました。
今回は「アルコールチェックは誰が行うのか」「どのようにチェックすればいいのか」など、白ナンバー事業者のアルコールチェックの方法について詳しく解説していきます。
目次
白ナンバー事業者のアルコールチェックの義務化とは?
通常、白ナンバーは自家用車や商用車、または自社の荷物を自社の車両で運ぶ際に適用されるナンバープレートを指します。緑ナンバーは、旅客または貨物の有償輸送を行う事業者が使用する車両に対して交付されるナンバープレートを指します。
従来アルコールチェックはバスやタクシー、トラックなどの緑ナンバー車両保有事業者(以下、緑ナンバー事業者といいます)で義務化されていましたが、2022年4月に施行された道路交通法の改正によって白ナンバー事業者にもアルコールチェックが義務づけられました。具体的な内容は以下のとおりです。
- 定員11名以上の白ナンバー車両を1台以上保有している事業者
- 定員10名以下の白ナンバー車両を5台以上保有している事業者(自動二輪車は1台を0.5台として計算)
- 運転前後のアルコール検知器によるアルコールチェックと記録の1年間保管義務
アルコールチェックが義務化された背景
白ナンバー事業者までアルコールチェック義務の対象が広がった背景には、2021年6月28日に千葉県八街市で起きた交通事故があります。本事故では、酒気帯び運転をしていた白ナンバーのトラックが下校中の児童5人を巻き込み、死傷者を出しました。
この事件を受け、同年8月4日に「通学路等における交通安全の確保及び飲酒運転の根絶に係る緊急対策」が発表されました。そのなかで、「安全運転管理者の未選任事業所の一掃や選任の促進」「乗車前後のアルコールチェック」などの対策概要が明記されています。
道路交通法施行規則を一部改正することで、運送業・タクシー業などの緑ナンバー車両を使用する事業者の義務だったアルコールチェックの対象を、規定台数以上の車両を保有している白ナンバー事業者にも拡大しました。
違反時の罰則
白ナンバー事業者のアルコールチェックの義務違反時の罰則は、道路交通法において以下のとおり定められています。
| <道路交通法> | ||
|---|---|---|
| 根拠 | 内容 | 罰則 |
| 第74条の3第1項 「安全運転管理者の選任義務」 |
自動車の使用者は、内閣府令で定める台数以上の自動車の使用の本拠ごとに、年齢、自動車の運転の管理の経験その他について内閣府令で定める要件を備える者のうちから、次項の業務を行う者として、安全運転管理者を選任しなければならない。 | 50万円以下の罰金 |
| 第74条の3第4項 「副安全運転管理者の選任義務」 |
自動車の使用者は、安全運転管理者の業務を補助させるため、内閣府令で定める台数以上の自動車を使用する本拠ごとに、年齢、自動車の運転の経験その他について内閣府令で定める要件を備える者のうちから、内閣府令で定めるところにより、副安全運転管理者を選任しなければならない。 | 50万円以下の罰金 |
| 第74条の3第5項 「選任、解任届出義務」 |
自動車の使用者は、安全運転管理者又は副安全運転管理者を選任したときは、選任した日から15日以内に、内閣府令で定める事項を当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。 | 50万円以下の罰金 |
引用元:『道路交通法施行規則第九条の十』
白ナンバー事業者のアルコールチェック方法

アルコールチェックの実施者
アルコールチェックは原則として安全運転管理者が実施する必要があります。安全運転管理者を選任していない場合は、選任および届け出等をする必要があります。
安全運転管理者の業務
警察庁の「安全運転管理者制度の概要」によると、安全運転管理者が行う業務は以下のとおりです。
| <安全運転管理者等の業務> | |
|---|---|
| 1 | 運転者の状況把握 |
| 2 | 安全運転確保のための運行計画の作成 |
| 3 | 長距離、夜間運転時の交替要員の配置 |
| 4 | 異常気象時の安全確保の措置 |
| 5 | 点呼等による過労、病気その他正常な運転をすることができないおそれの有無の確認と必要な指示 |
| 6 | 運転者の酒気帯びの有無を目視などで確認のほか、アルコール検知器を用いて確認 |
| 7 | 酒気帯び状態に関する確認結果の記録と1年間の保存に加え、アルコール検知器を常時有効な状態にしておくこと |
| 8 | 運転日誌の備え付けと記録 |
| 9 | 運転者に対する安全運転指導 |
(引用:警察庁『安全運転管理者制度の概要』)
また「酒気帯び状態に関する確認結果の記録と1年間の保存」では以下項目を保存する必要があります。
| <記録内容> | |
|---|---|
| 1 | 確認者名 |
| 2 | 運転者名 |
| 3 | 運転者の業務に係る自動車の自動車登録番号又は識別できる記号、番号など |
| 4 | 確認の日時 |
| 5 | 確認の方法(アルコール検知器の使用の有無/対面でない場合は具体的方法) |
| 6 | 酒気帯びの有無 |
| 7 | 指示事項 |
| 8 | その他必要な事項 |
(引用:警察庁『道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令の施行に伴うアルコール検知器を用いた酒気帯びの有無の確認等について(通達)』)
2023年12月から、安全運転管理者による運転者の確認において、従来の目視確認に加え、アルコール検知器を使用した確認が義務化されています。「直行直帰」「長距離運行」などで目視確認が難しい場合は、運転者に携帯型アルコール検知器を携行させたうえで、ビデオ通話のような対面に準ずる方法で実施することも可能です。非対面の場合の具体的な確認方法として、以下のようなものがあります。
- カメラ、モニター等によって、安全運転管理者が運転者の顔色、応答の声の調子等とともに、アルコール検知器による測定結果を確認する方法
- 携帯電話、業務無線、その他の運転者と直接対話できる方法によって、安全運転管理者が運転者の応答の声の調子等を確認するとともに、アルコール検知器による測定結果を報告させる方法
(引用:警察庁『道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令の施行に伴うアルコール検知器を用いた酒気帯びの有無の確認等について(通達)』)
しかしこのようなケースでは、なりすましや検査結果の改ざんリスクが高まります。遠隔でのアルコールチェックに対応したシステム導入をするのも手段のひとつです。
まとめ
2023年12月から国土交通省によって白ナンバー事業者にアルコールチェックが義務づけられたことで、運転者は1日2回のチェックが必要となり、安全運転管理者は幅広い業務への対応が必要になりました。
効率よく確実に対応していくためには、正確かつ信頼性が高いアルコール検知器の活用とともに、なりすましや検査結果の改ざんリスクに対応した点呼システムの導入が必要です。
当社では遠隔でのアルコールチェックに対応したクラウド型点呼システム「Cagou IT点呼 for 白ナンバー」を提供しております。ご気軽にお問い合わせください。
製品情報
関連リンク
- IoTサービスページ
- 内閣府『道路交通法施行規則第九条の十』
- 警視庁『安全運転管理者制度の概要』
- 内閣府『「通学路等における交通安全の確保及び飲酒運転の根絶に係る緊急対策」の進捗状況について』
- 警視庁『安全運転管理者による運転者に対する点呼等の実施及び酒気帯び確認等について (通達) 』
※本記事の記載内容は2025年3月現在のものとなります。
※本事例で記載されている会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。